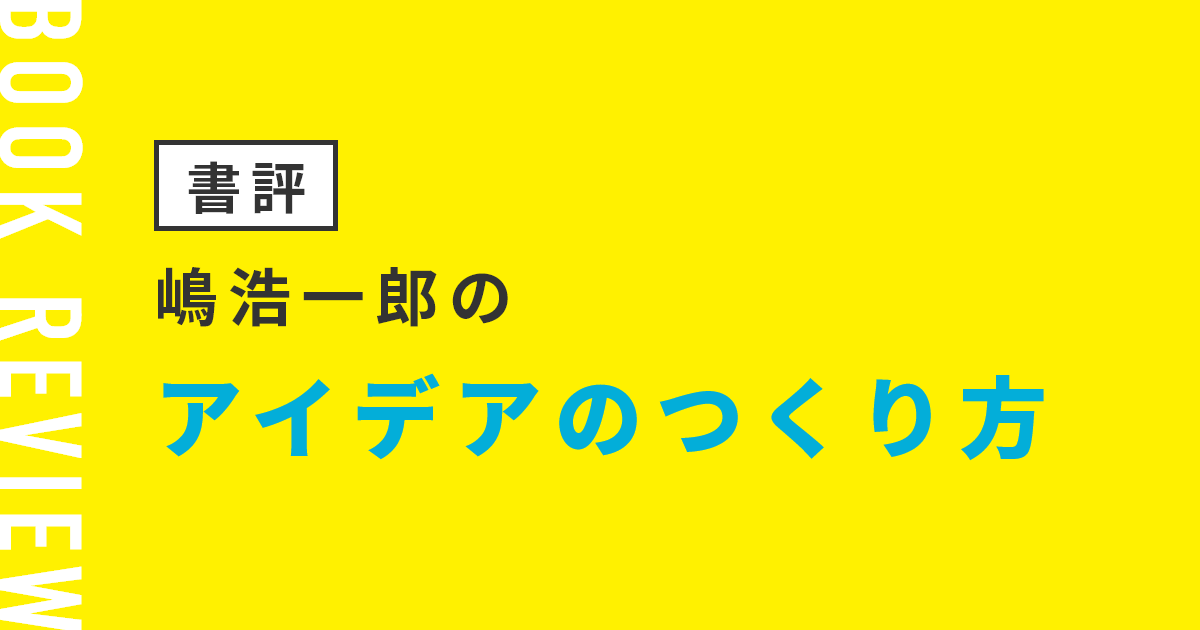「嶋浩一郎のアイデアのつくり方」を読んだので、解説していきます。
この本がおすすめな人
- 企画に携わる人
- 興味関心領域を広げたい人
- 話せる話題が少なく雑談が苦手な人
- 片付けられないことを悩んでいる人
紹介されている情報収集法を行うメリット
興味関心領域が自然に拡大する
最初は自分の興味のある分野の羅列になるかもしれません。
ですが、メモを取り続けるうちに、自分の興味のある情報が他の分野と結びつき、次第に興味の範囲が広がっていきます。
メモ魔をしていて感じるのは、メモを楽しんで取ると情報をキャッチするアンテナが敏感になり、面白そうな情報をキャッチしやすくなるということです。
自分が興味のある情報が増えるので、人生が少し楽しくなります。
義務的にやってしまうと全く楽しくないので注意が必要です。
雑談力
「話題が尽きてしまう」「何を話したら良いのかわからない」といった理由で雑談が苦手な場合は、この本で紹介されている情報収集を続けることでお悩みが解決するかもしれません。
トークのテーマになっている関連情報を手帳に記した情報の中からピックアップしたり、受けそうだなと思う情報を話してみたり。
情報の範囲が狭い最初のうちは難しいかもしれませんが、続けていくことで様々な分野の情報が集まり、雑談のネタにできます。
プレゼン力
情報収集を続けることで、似たようなシチュエーションや過去事例を話しやすくなったり、状況を比喩的に説明できるため話の説得力が増します。
企画力
課題の解決や、新規事業の企画など現代で何かと必要な企画力。
さまざまなジャンルの情報を1冊のノートに集めるため、見知らぬ情報が出会いやすくなり、多少の訓練は必要ですが、新しい企画を生み出しやすくなります。
アイデアを作る3ステップ
アイデアは以下の3ステップで生まれます。
- 情報収集
- 情報の放牧
- 化学変化
必要なもの
アイデアを作るため用意する必要があるのは以下の3つです。
- ノート
- ペン
- ふせん
ノートは将来的に一軍と二軍の2冊必要ですが、初期段階では1冊で問題ありません。
ふせんは印刷物から情報収集をするときに使います。
お気に入りの文具を使うとメモが楽しくなりますよ。
とにかく集める!情報収集
自分のペースで、本で読んだこと、テレビやラジオ、人から聞いた話など、気になったり、知らなかった情報をすべて収集します。
第2段階で取捨選択をするため、集める情報が多すぎても問題ありません。
どんな情報を集めるのか
著者は以下のような情報を集めているそうですが、以下に当てはまらなくても気になった情報を収集しても良いです。
このとき、集めた情報に「ファクト・事実」などと分類する必要はありません。
- ファクト・事実:トリビアのようなものや史実、業界ネタなど
- オピニオン・意見:評論家の意見や、新鮮で斬新な意見だと思ったネタ
- アナリシス・分析:今まで見聞きしなかったユニークな分析
- 示唆・疑問:オピニオンやアナリシスほど定かではないものの、なにか示唆を感じさせる情報で、本の中で著者、主人公が疑問に思ったことなども含む
「?」や「~かもしれない」など推測を含ませるものが多い - 表現:これは使えると思える文章表現や、たとえ、比喩、名言、広告のキャッチコピーなど
情報を集めるときの注意点
情報源を明記する
その情報は本物なのか偽物なのかよりも、たとえば、インターネット総合掲示板「2ちゃんねる」でそう言われたという“事実”が重要
嶋浩一郎のアイデアのつくり方
情報の真偽はその情報が必要になったときに検証すれば問題ありませんし、情報源を明記することで検証が可能です。
情報収集に集中しましょう!
情報は差別しない
芸能ゴシップも、考古学の発見も、コミケで売られている同人誌で書かれていたことも、すべて等価。情報には一流も三流もない。
嶋浩一郎のアイデアのつくり方
違うジャンルの情報を掛け合わせることでよりギャップのある、インパクトが大きいアイデアが生まれます。
とにかく分け隔てなく躊躇なく情報は集めるのです。離れたものがくっつくほど、価値は大きくなるのですから。
嶋浩一郎のアイデアのつくり方
情報のマーキング方法
書籍や雑誌などの印刷物の場合
新しい情報に出会ったら、「付箋を貼る」だけです。
著者おすすめの付箋は3Mの「フラッグポインター」で、細いため該当の行がわかりやすく、半分が無色透明なので貼ったまま文章を読むこともコピーを取ることもできるなど付箋自体の使い勝手が良く、ケースが名刺サイズで持ち運びやすく、本のしおりとしても活用できるそうです。
ただ、こちらの商品は出版年が古い(2007年)ということもあり、廃盤になった可能性があります。
商品名は違いますが、似た商品は存在していました。

電子書籍を利用している場合は、マーカー機能などを利用しても良いですね。
それ以外の情報のマーキング
映画や会議の席で聞いた話など印刷物以外の情報は、「二軍ノート」と読んでいるメモ帳に書き記します。
「二軍」ということは「一軍」も存在しており、二軍ノートは一軍ノートよりも大きめだそうです。一軍ノートの使い方は後ほどご紹介します。
注意点でもご紹介しましたが、情報源も同時に記録することが重要です。
もちろん、情報源ごとに分類する必要は全くなく、集めた順番で書き記すだけです。
寝かせて、並べる。情報の放牧
読み終わった本や、二軍ノートに書かれた情報は大体一ヶ月寝かせておくのです。まるで、ウイスキーやワインの熟成のように。そう、ウイスキーやワインのように、情報もここで寝かせると、シッカリとした味わいが出てくるのです。
嶋浩一郎のアイデアのつくり方
情報収集が終わったら情報を放牧する段階に入りますが、すぐに一軍ノートに書き写すのではなく、1か月ほど寝かせてから書き写します。
ウイスキーやワインのように、情報も寝かせることでしっかりとした味わいが出てくるそうです。
1か月ほど寝かせたら、言葉を知らなかったから集めた情報なのか、事実が面白かったのから情報なのかを思い出して一軍ノートへ情報を書き込みます。
その情報を集めた理由を思い出すことで、情報を記憶に深く刻み込み、なんとなくこんな情報があったはずとうっすら思い出せるようになります。
面白い情報が連鎖するんじゃないかという勘が働くときや、元の情報が薄いときは、ネットで関連情報を探し「おまけ情報」をつけることでより記憶に深く刻み込めたり、情報自体が面白いものになります。
書き込む際も整理はせず、知った順、気になった順に情報を並べます。
情報は生のまま、何のラベルもつけないままに牧場の中に放置しておくのが一番なわけですから。単純にナンバーだけをつけていきます。
嶋浩一郎のアイデアのつくり方
情報を掛け合わせ、活用することを考えたときに、ナンバーがあると「〇〇番と××番を掛け合わせると良さそう」といったメモなどはしやすいのではないかなと思いました。
特定の本の情報を書き写すとある番号の付近には、その本に内容に関連する情報が続きますが、全体を見渡したときに、さまざまなジャンルの情報が存在すれば問題ありません。
書き込みの頻度やタイミング
期間を決めてちゃんとやるというより、一週間に一回くらい、なんとなく、机の周り、ベッドの周りに、付箋のついた本や雑誌が溜まってきたら適当に書き写しアワーをつくります。
嶋浩一郎のアイデアのつくり方
義務化するとやる気がなくなる人にとっては気楽で良いですね。
予想外の出会いとアイデアの誕生。化学変化
企画を立てるためには、多くの関連情報を集めることも大事ですが、その多数の情報の中から本質的に必要な情報を選んでシナリオを作っていくことが要求されます。
手帳にならぶ一見何の関係もない情報同士に、気づかなかった関係性を発見して、さらに二つの情報の上位概念をつくり出すことはそう簡単なことではありません。
嶋浩一郎のアイデアのつくり方
そこで、全く関係ないキーワードを「なぞかけ」のように結びつけ、上位概念をつくる訓練を行うことで、異なる情報をまとめるプロセスにクリエイティブティが発揮されます。
情報をかけ合わせる練習法
練習法はシンプルで、「本屋に平積みされている本」や「電車の中の週刊誌の車内吊り広告のタイトル」を無理やり掛け合わせて、ひとつの言葉にまとめるだけです。
具体的には以下のような手順で行います。
- 隣り合わせのタイトル同士をひとつのキーワードで表す
- 生まれたキーワード同士をさらに上位のキーワードで表す
- 最終的にひとつに集約されたキーワードが一週間の見出し
思い込みや既成概念をなくすことが大切です。
パソコンではなく紙のノートを使う理由
情報を掛け合わせてアイデアを作るために一番大事なのはパッと素早く多くの情報に目を通すことができる一覧性です。
パソコンは検索性には優れていますが、目的が決まっていない情報の掛け合わせには不向きのため、物理的にページをめくっていけるため手帳がおすすめです。
著者は「モールスキン」の手帳を使用していると書籍内で記載されていましたが、おそらく「モレスキン」の手帳もしくはノートなのではないかなと思います。
クロス×「嶋浩一郎のアイデアのつくり方」
一軍ノートはともかく、二軍ノートはメモアプリの1つのページに書くなどのルールを作り、整理しないというルールさえ守れば、パソコンやスマホを使っても良いのではないかなと感じました。
イラストを使いづらいことや、充電がなくなってしまうとメモが取れないのはデメリットなので、100%目的を果たせるとは言えませんが。